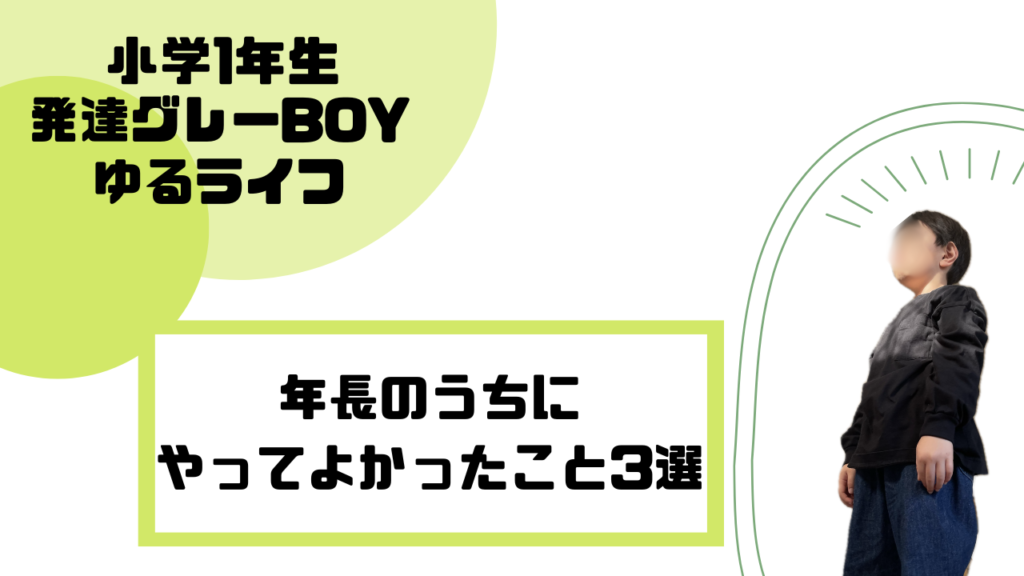
【目次】
1. 支援級 or 普通級?迷ったらまずやってよかったこと
2. 放課後等デイサービス、出遅れて後悔…!
3. これはやればよかった!生活リズム&時間感覚の慣らし
4. まとめ|“ゆるっとでも早めに”がカギ
1. 支援級 or 普通級?迷ったら…やってよかったこと
保育所で加配がついていたこともあり、
「支援級になるのかな?普通級でいける?」とずっとモヤモヤしてた私。
先生に相談してみたら、
「入学予定の学校に見学行ってみたら?」とアドバイスをもらって、
年長の夏前(7月ごろ)に学校見学へ。
実際に行ってよかったポイントは、
• 支援級と普通級の環境の違いを“目で見て”感じられた
• 普通級の先生や支援級の先生と直接話せた
• 子どもが通うかもしれない環境を知ることで、親の気持ちも整理できた
しかも見学を早めにしたことで、10月の就学前健診のときにもスムーズに話が通じたのが大きかった!
2. 放課後等デイサービス、出遅れて後悔…!
うちは民間の学童と放デイ、
どっちにするか悩んでいたら動き出しが遅れてしまって、
実際に動いたのは年長の11月。
結果、人気のあるところは満員で、
選べる状況じゃなく「空いてるところに…」
という消極的な選び方になってしまった。
(結果今は息子も楽しんで通ってるのでよかったですが)
放デイも場所・方針・特性が本当にそれぞれ違うから、
• 送迎があるか?
• ワーママにとって通わせやすいか?
• 療育の方針が我が子に合っているか?
など、
“自分たちにとっての条件”を整理して見学&比較することが本当に大事!
→ おすすめの時期は夏〜秋までに動き出しておくこと!
ゆっくりしてると方デイの枠も無くなってくるから、早めに!

3. これはやればよかった!生活リズム&時間感覚の慣らし
これは完全に「もっと早くやっておけば…!」と後悔したこと。
保育所では遊び中心の生活だったから、
小学校での「時間で動く生活」や「読み書き中心の勉強」が息子にはかなりハードル高くて…。
特にうちは読み書きへの興味が薄く、苦手だったのもあり、
入学後すぐに授業についていくのが難しい状態に。
「今思えば…」だけど、
• 読み書きの導入(遊び感覚で文字に触れるとか)
• 朝の起床時間や支度の流れを“学校モード”に慣らす
• 小学校ごっこで「座って話を聞く」などの練習
を年長のうちから、もっとゆるくでも取り入れておけばよかったな〜と思ってます。

あとは、
時間内に終わらせる“ペース感”の練習
特にうちの子は「マイペースで自由に進めたいタイプ」だったから、
「なんで途中でやめなきゃいけないの?」と戸惑って、
学校のペースに合わせるのにすごく苦労した…。
だから、
• 給食の時間(〇分以内で食べる)
• 勉強・遊びの時間(時間を区切って行動する)
といった“時間内に終わらせる習慣”を意識する練習が大切だなと実感。
→ タイマーを使って「あと〇分でお片付け」や、
「今から〇分集中しよう」など、
おうちでできる小さな練習を日常に取り入れておくと◎

4. まとめ|“ゆるっとでも早めに”がカギ!
就学前って、やらなきゃいけないことが本当に多くて、
ママもパンクしそうになるよね。
私も「まだ早いかも」と思ってるうちに
気づいたら年末で、焦って動いたタイプ(汗)
でも、1つでも先に動いておくと、気持ちも行動もグッとラクになる!
無理しなくてもいいけど、
「ちょっと調べてみる」「見学の電話してみる」そんな一歩が、あとあと大きな安心につながるよ。